
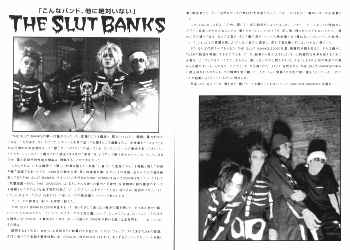

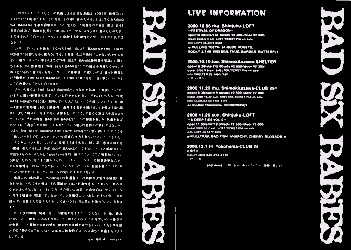

日付 : 不明
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
THE SLUT BANKSの第一印象はコレだった。怒涛のごとき轟音と、際立つメロディ。闇雲に暴力的なのではなく”力があるくせにラフ”で、どのパートを耳で追っても聴き所満載なのに、全体をとらえようとすれば圧倒的な存在感をもって”歌”が、”メロディ”が迫ってくる。ロックン・ロールの歴史を彩ってきたバンドたちや、ジャンルとして確立された過去さまざまの”革命”を、どうやって掛け合わせたらこういうことになるのか。僕の前時代的性能な頭脳は、理解することが出来なかった。 しかしそれは、いわば緻密で小賢しい計算を超えた”本能”に基づいた音楽だからこそ発散しえた”判別不能”加減でもあったのだ。1996年の生誕以来、常に加速度を増しながら、その本能にまかせて己の道を失踪してきたTHE SLUT BANKS。ギタリストに弐代目STONE STMACを迎えて2000年3月にリリースされた『死霊遊戯〜EVIL THE DRAGON』は、まさにそんな彼らの魅力と可能性、反骨精神と創作意欲のすべてを凝縮させたかのような金字塔的作品だった。このアルバムをチャート上位に送り込み、国民的メガ・ヒットにいたらしめなかったのは、日本のロック史にとっての致命傷だったという気さえする。 そして、その終焉は、余りにも突然に訪れた。 THE SLUT BANKSは2000年夏をもって、自ら決して長くない歴史に幕を閉じた。元々あの世から蘇ったゾンビたちなのだから・・・というコンセプチュアルな話は置いといて、とにかくコレは、ロックにとって大きな損失になりかねない大事件なのである。なにしろ彼は、2000年が終わる頃には全世界を・・・。ま、いいか、その話は。 説明するまでもなく、あまりに突然なその終幕の引き金となったのは、ボーカリストであるTUSKの脱退。次作に向けての名曲を量産体制にあったDUCK-T改めDUCK-LEEをはじめとするメンバーたち、バンドを取り巻く関係者たち、そして当然ながら熱狂的支持者たちにとっても、これはまさに”寝耳に水”の出来事だった。 しかしDUCK-LEEは、この件に関して一切の説明をしようとはしない。曰く、「だってホントの理由なんんてアイツ自身しかわかんねぇじゃん。俺たちがクビにしたわけでも、逆に取り残されたんでもないんだし」。確かにその通りである。なんたる潔さ。そして懐の深さ。バンドの致命傷となり兼ねないフロントマンの脱退について、これ以上言葉を発しようとしない彼の心意気に、思わず酒を奢らずにはいられない僕だった。 そう、ならば代弁させてもらおう。THE SLUT BANKSは2000年夏、発展的分裂を迎えた。それは確かにTUSKの脱退を発端とするものではあった。が、結果から見ればそれは「もっと刺激的な未来を迎えるために必要なこと」でしかなかった。もちろん、悔しくはないのかと問われれば、少なくとも8月上旬の時点で僕ならば頷かずにはいられなかっただろう。が、今は違うのだ。それは、当然ながら、THE SLUT BANKSの歩みに終止符を打ちながらも、その精神を受け継ぐどころか、さらに発展させる形で前に進もうとしている、このバンドが始動しようとしているからに他ならない。 声高らかに迎えてくれ。誰もまだ、聴いたことも観たこともないバンド、BAD SiX BABiESの生誕を! BAD SiX BABiESは、日本のロック・シーンの人脈図を描こうとしたならば、間違いなくTHE SLUT BANKSの真下、もしくはすぐ横に名を記されるべきバンドだ。すでに潜伏期間中からインターネット等で情報が交錯していただけに改めて紹介する必要もないとは思うが、念のため4人のメンバーの名前を記しておく。 高木 フトシ(vo) 石井 ヒトシ(g) 戸城 憲雄(b) 新美 俊宏(ds) ここにはTUSKはおろか、DUCK-LEEもSMOKIN' STARも、弐代目STONE STMACも存在しない。名を連ねているのは、霊界からマジに生身で蘇ってしまった3人の男たち(・・・もういいか、こういう話は)と、初めて彼らと交わることとなったフロントマンである。 高木フトシは THE HATE HONEYでの活動でも知られるボーカリスト。THE SLUT BANKSとはライブでの共演歴もあるが、当時から戸城は、彼のスタイリッシュなクールさに一目を置いていたという。 「歌がどうだったかよく覚えてねぇんだけど、カッコいいと思ったことだけは確か」と戸城は言う。たんたるいい加減さ、と感じる人もいるだろう。しかしこれに続く彼の言葉を読めば、誰もが納得するはずだ。曰く、「だけど歌がしょ〜もなかったら、カッコいいと思わねぇじゃん」と。 いつかどこかで聞いた台詞だと思ったら、THE SLUT BANKSに弐代目STONE STMACこと石井ヒトシを迎えた時にも、彼は同じことを口走っていたのだった。「音楽の趣味が合うのは酒の席でわかってたけど、考えてみたらギター弾いてるのはろくに聴いたことがなかった」と。しかしこの、彼の動物的ともいうべきカンの確かさは、過去の幾つもの実例によって証明されている。ギャンブルはハズすことも多々ある彼だが、その”カッコいいロックン・ロール”の探査力は並大抵のものではない。 彼にとって、ボーカリストの音域がどうのとか、ギタリストがどれだけ速く弾けるかとか、ドラマーがどれだけデカい音を出すかとか、そんなことは意味を持たないのだ。要はカッコいいか悪いか。「カッコいい」と感じることは、すなわち、仮に他に欠点があったとしても、余りある説得力がそこにあるということなのだから。 そしてその「カッコ良さ」に御墨付きをもらった高木もまた、戸城と同様、もしくはそれ以上に”何もせずにいること”が堪えられない性分の持ち主だった。新しい刺激、もっと強烈な何かを求めていたのだった。 高木が籍を置いていたTHE HATE HONEYは、現在活動休止中。今後、再始動の可能性が全くないわけではないが、彼自身の中で同バンドとの関係は、すべて”過去完了形”のものとして精算されている。そして戸城は「だからこそ誘った」と言い、意味深長な笑みを浮かべながら「一応、それはルールだからさ」と続けた。 このラインナップ、そしてこの名義による正式な活動は、10月5日、新宿ロフトでのライブを起点とすることになる。その場に居合わせることは、すなわちBAD SiX BABiESの生誕を目撃することと、全くもって同様なのである。実は、去る8月末の時点で、職権を乱用して彼らのリハーサル・スタジオに潜入したのだが、その生まれたてのバンド・サウンドの発散する刺激性たるや、これまでの比ではなかった。 いや、このバンドを過去、すなわちTHE SLUT BANKSやTHE HATE HONEYと比較しながら語ろうとすことこ自体、もはや愚行でしかないのかもしれない。確かにメンバー中3人まではTHE SLUT BANKS最終章を見届けた男たちである。その音楽性も、THE SLUT BANKSとしての過去が存在したからこそ成り立つものと言えなくもない。が、ここで重要視してほしいのは、彼らが現在という瞬間を、としての新しい章ではなく、全く新しいバンドとしての序章としてとらえている点だ。 ファンの多くは、THE SLUT BANKSという存在が消滅した事実について、いまだに重い衝撃を引きずっているのかもしれない。それはもちろん、THE HATE HONEYの行く末に期待していた人たちにとっても同じことだろう。が、彼らは従来の支持層に対して無条件に通用する名前を揚げることを敢て自ら拒否し、決して軽々しいはずのない決意をもって、こうした新たな旅立ちを迎えようとしている。それは現在、BAD SiX BABiESとしての現実を楽しみ、刺激をおぼえつつも、”過去”を大切にしておきたいという彼らの気持ちの表れではないか。つまり、THE SLUT BANKSもTHE HATE HONEYも、闇に葬られたのではなく、新しい形での、よりポジティブな前進の仕方をみつけたということなのだ。 ちなみにバンド名については、詮索するまでもなく、特に深い意味を持たない模様。考えてみれば、THE SLUT BANKSだってそうだった。4人編成なのに何故SiXなのか。もしかしたらsickとchicを引っ掛けて”シックス”の複数形としてこう表記したのか。はたまた誰かさんの、ニッキー・シックスへの敬意表明なのか。そんな推理はこのさいどうでもいい。とにかくこのバンド、名前を見ただけで、やたらといかがわしいロックン・ロールの匂いがするではないか。 幸運にも、都内某ローカル駅近くの居酒屋でこの名前が決定する場面に居合わせたことができた僕は、その猥雑かつ強い刺激性をもった匂いに、思わずむせかえりそうになった。そして今、その匂いに反応した自分のロックン・ロールに対する嗅覚が、間違っていなかったことを確信しつつある。おそらく今、これを読んでいる皆さんのほとんどが、ごく近いうちに同じ思いを味わうことになるはずだ。 そして次の瞬間、間違いなくこう確信するはずだ。「こんなバンド、他に絶対いない」と。「絶対、いるはずがない」と。酒さえ入れば「コレをやらせりゃ俺様が世界一!」と豪語するあの男が、絶対的な信頼を寄せるメンバーたちと手を組んでの”悪だくみ”がいよいよ本当に刺激的でスリルに満ちた局面を迎えようとしている。 増田 勇一 [ 2000年9月 ]
|